
パパママ育休プラスとは、育児休業の期間が子の年齢が「1歳2か月に達するまで」に延長される制度です。両親がともに育児休業を取得する等、複数の条件を満たすと利用できます。
企業にとって、パパママ育休プラスの導入はさまざまなメリットをもたらすため、内容や運用のポイントを把握しておきましょう。
パパママ育休プラスの内容と企業にとってのメリット、運用での注意点を解説します。
| この記事でわかる事 |
|
|
「採用手法の比較表/自社にあった採用手法の選び方」をまとめたe-bookを無料提供中
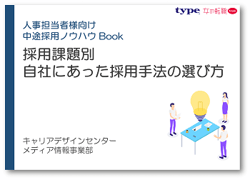 |
1.パパママ育休プラスとは? |
パパママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合、条件を満たすことで、対象となる子の年齢が「1歳2か月に達するまで」に育児休業の取得可能期間が延長される制度のことです。
2010年6月より施行されているパパママ育休プラスは、父親の育児参加を促すとともに、母親の職場復帰をサポートする目的があります。
(1)通常の育児休業との違い
通常の育児休業は、子が「1歳に達するまで」取得できます。保育所等への入所ができなかった場合などには、1歳6か月から2歳までの延長も可能です。
一方のパパママ育休プラスは、「1歳2か月に達するまで」育児休業を取得できるため、通常の育児休業と比べて取得可能期間が長いという違いがあります。
(2)パパママ育休プラスの取得期間
パパママ育休プラスの取得期間は、子が「1歳2か月に達するまで」です。
ただし、一人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業・出生時育児休業含め1年間)は変わらないため、例えば母親が産後休業含め、1年2か月の育休を取得することはできません。
なお、通常の育児休業と同様に、条件を満たした場合は子が2歳になるまで休業の延長が可能です。
(3)パパママ育休プラスの取得条件
パパママ育休プラスの取得条件は、下記のとおりです。
取得条件
|
パパママ育休プラスを取得できるのは、配偶者の育児休業の初日よりもあとに育休を取得した父親や母親です。
そのため、例えば父親がパパママ育休プラスを利用する場合は、母親の育児休業開始日よりもあとに育児休業をとる必要があります。ケースによっては、夫婦でパパママ育休プラスを取得することも可能です。
なお、パパママ育休プラスは「育児休業を取得すること」が条件のため、夫婦のいずれかが専業主婦(夫)やフリーランス、自営業などで育児休業を取得できない場合は対象外です。
2.パパママ育休プラスの企業にとっての導入メリットと効果 |

パパママ育休プラスを導入すると、企業にとって次のようなメリットや効果が期待できます。
|
どのようなメリットがあるのか、詳しく解説します。
(1)従業員満足度・エンゲージメントの向上
パパママ育休プラスの導入は柔軟な育児につながるため、従業員満足度やエンゲージメントが向上するメリットがあります。
出産・育児は、従業員にとって大きなライフイベントであり、すくすくと成長する子供との触れ合いは一瞬一瞬が大切な思い出です。
従業員は、父母ともに育児に携われる環境を整備した企業に対して満足し、さらに貢献しようと思えるでしょう。
(2)優秀な人材の定着と採用力強化
パパママ育休プラスを導入すると、従業員は配偶者と協力しながら育児ができ、ワークライフバランスを保ちやすくなるため、自社への定着率が高まります。
従業員の定着率が高い企業は、「働きやすい職場」というイメージを求職者に与え、就職先として選ばれやすくなるでしょう。労働人口が減少し続けている日本の現状を踏まえると、採用力を強化して競争優位性を確保することは重要です。
| 💡定着率の高い会社の特徴と高める方法についてまとめた記事はこちら |
(3)企業のイメージアップと多様な働き方の推進
従業員の働きやすさが向上する制度を多く導入・整備している企業は、社会的に高評価やポジティブなイメージを得やすいです。従業員のライフイベントを考えている企業として、応募やファンも増えるでしょう。
また、育児休業は2回に分割して取得可能なため、パパママ育休プラスを利用すれば夫婦で4回にわけて交代で育児をする、仕事が忙しい時期だけ復帰するなど、柔軟で多様な働き方ができます。
| 💡自社の良いイメージの伝達&ファン化させる活動についてまとめた記事はこちら |
3.パパママ育休プラスを導入・運用する上での注意点 |

パパママ育休プラスを導入・運用する際には、就業規則の改定や業務体制の整備などが求められます。
押さえておきたい次の3点について解説します。
|
(1)就業規則の改定
パパママ育休プラスを導入する際には、就業規則の改定が必要です。例えば、パパママ育休プラスについて次のように記載できます。
パパママ育休プラスの就業規則への記載例
|
また、育児休業申出書にもパパママ育休プラスの文言を載せる、配偶者の休業開始(予定)日の記載欄を作るなどの対応も必要です。
従業員に誤った認識を与えないように、従業員が理解しやすい言葉かつ正確性を意識して記載しましょう。
(2)業務体制の整備と人員配置の工夫
従業員がパパママ育休プラスを取得しやすいように、業務体制の整備と人員配置の工夫も求められます。
政府は、両立支援等助成金のひとつに「育休中等業務代替支援コース」を設けています。育児休業取得者の業務を代替する従業員に対して手当を支給する企業や、新規で人材を雇用した企業に対し、助成金が支給される制度です。
育児休業することに後ろめたさを抱く従業員や、仕事の負担の増加に不満を覚える従業員がいるかもしれないため、気兼ねなく育児休業できたり気持ちよく働けたりする環境を作れるように、助成金の活用もオススメします。
| 💡両立支援等助成金の種類についてまとめた記事はこちら |
(3)従業員への周知と取得促進のポイント
パパママ育休プラスの取得メリットや対象者、期間、申出期限と部署などについて、データ・書面での配布や研修などを行い、従業員へ周知します。相談窓口も設けると従業員の安心感につながるでしょう。
意向確認も兼ねた場合、従業員から取得の意向をスムーズに引き出せます。厚生労働省の資料「就業規則への記載はもうお済みですか」に周知・意向確認書の例があるため、参考にするとイメージを掴みやすいです。
より多くの従業員がパパママ育休プラスをポジティブな気持ちで取得できるように、取得申請者に対して企業からのお祝いを用意する、周りの従業員へ金品を支給して不満をなくすなどの対応も求められます。
|
「採用手法の比較表/自社にあった採用手法の選び方」をまとめたe-bookを無料提供中
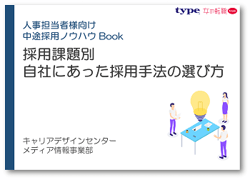 |
4.人事担当者が押さえるべき申請手続きと必要書類 |

従業員は、パパママ育休プラスの利用中に育児休業給付金を受け取ることができます。
人事担当者は従業員に不利益が生じないように、申請手続きと必要書類、育児休業給付金などについて押さえておくことが大切です。
下記3つの観点から解説していきます。
|
(1)申請の流れとスケジュール
従業員がパパママ育休プラスを利用しながら育児休業給付金を受け取るには、対象の子が1歳になる前に育休を取得する必要があります。そのため、就業規則に「育休の申請は育休開始日の1か月前に行う」旨を記載しておくと、時間的余裕があり安心です。
原則として、企業が管轄のハローワークへ申請を行います。申請手続きの際には、「受給資格の確認」と「初回の育児休業給付金の支給」を同時申請できます。同時申請の場合の提出期限は、育児休業開始日から起算して4か月後の末日までです(例:育休開始日が4月10日の場合、提出期限は8月31日)。
育児休業給付金の支給は2か月に1回のため、2か月ごとにハローワークへの申請が必要です。申請後、支給決定となった場合、ハローワークから「育児休業給付金支給決定通知書」と「(次回申請用)育児休業給付金支給申請書」が送付され、次回以降の申請では「次回申請用」を使用します。
(2)必要な書類と記入時の注意点
パパママ育休プラスの申請の際に必要な書類を以下にまとめました。
|
パパママ育休プラスを利用する場合は、「(初回)育児休業給付金支給申請書」の27欄、28欄に記入が必要です。28欄に配偶者の被保険者番号を記入しますが、配偶者が公務員等で雇用保険の被保険者でない場合は記入不要です。
また、必要書類⑥に関しては、支給申請書に配偶者の被保険者番号が記載されており、配偶者の育児休業給付受給の有無が確認できる場合は必要ありません。
(3)育児休業給付金と社会保険料免除
育児休業給付金の支給要件や社会保険料免除についてまとめています。
-
育児休業給付金の支給要件と支給額
育児休業給付金の支給要件は下記のとおりです。
|
支給額の割合は、育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%で、具体的な計算方法は下記のとおりです。
|
休業開始時賃金日額は、育児休業開始前の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。なお、上限・下限額が決められています。
-
社会保険料の免除
育児休業中は、申出によって従業員・事業主負担分ともに、健康保険・厚生年金保険料が免除されます。社会保険料の免除申請は企業が行います。「育児休業等取得者申出書」を作成して、育児休業の期間中または育児休業の終了日から1か月以内に、管轄の年金事務所または事務センターへ提出が必要です。
なお、社会保険料免除となっても、保険料は支払ったものとみなされます。将来的に受け取る年金額への影響はないため、従業員に説明すると安心感を与えられるでしょう。
5.パパママ育休プラスの活用で働きやすい職場を作るポイント |

従業員がパパママ育休プラスを活用できるような働きやすい職場を作るには、次の2つが必要です。
|
自社の体制を見直し・改善して、よりよい職場環境を作っていきましょう。
(1)育児休業復帰後のキャリア支援
育児休業取得にあたり、従業員は自身のキャリアについて不安を感じやすいです。従業員がキャリアへの希望を持ったまま育児休業を取得できるように、休業前から面談を行い、キャリアに対する考えなどを把握しておきましょう。
復帰後には、従業員が希望するキャリア開発に向けた業務や育成方針を示します。キャリアに関する相談も受け付け、従業員の理想のキャリア実現をサポートすることが大切です。
育児休業に関して従業員をどのように支援すればいいかわからないという場合は、厚生労働省の「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を活用すると進め方やチェックポイントの参考になります。
(2)従業員間のコミュニケーション
日頃から従業員間のコミュニケーションを密にしておくと、お互いの仕事の状況がわかるため、協力体制が醸成されます。また、お互いに声をかけやすい環境は職場の雰囲気もよく、育児休業も取得しやすいです。
育児休業中の従業員とのコミュニケーションも重要です。育児休業中の従業員は、職場から離れることで仕事の情報を得られなくなり、疎外感を覚えることがあります。そのため、自宅にいてもイントラネットや社内報などで社内の情報を得られる体制を整備し、職場の変化から置いていかないことが求められます。
また、人事担当者と育児休業取得者が必要な手続きをスムーズにやり取りできるように、チャットなどの気軽なコミュニケーションツールを取り入れることも効果的です。
6.まとめ |
パパママ育休プラスを導入すると、従業員は子が1歳2か月になるまで育児休業を取得できるようになるため、従業員満足度の向上につながるでしょう。自社のアピールポイントにもなり、採用力強化やイメージアップするメリットもあります。
従業員のパパママ育休プラス利用に関する手続きを不備なく進められるように、申請の流れや概要などを把握しておくことが大切です。また、従業員とのコミュニケーションを密にして、安心感も高めていきましょう。
参考:
厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」
厚生労働省「「パパ・ママ育休プラス」にかかる必要書類」
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」
いかがでしたか。もし中途採用について悩まれている、自社にとって適切な手法が分からないといった場合は、ぜひ弊社キャリアデザインセンターにご相談ください。エンジニア採用・女性採用に特に強みを持ち、あらゆる中途採用ニーズに対応できるサービスを運営しております。
サービスの詳細については、下記弊社中途採用サービス概要のご案内ページをご覧ください。
#パパママ育休プラス #育休
|
type公式中途採用向けサービス案内サイト 【公式】type中途採用向けサービスのご案内|転職サイト、転職エージェント、派遣サービスなど 運営会社 株式会社キャリアデザインセンター 会社概要 コーポレートサイト:https://cdc.type.jp/
事業内容
・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営 ・転職フェアの開催 ・人材紹介事業(厚生労働大臣許可 13-ユ-040429) ・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス ・パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業 ・IT業界に特化した人材派遣サービス(厚生労働大臣許可 派13-315344) ・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営 など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。
法人企業様向けお問い合わせ先
・フォームでのお問い合わせ |
著者プロフィール
ブログ編集部
「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。
■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/
■企業様向け公式SNS:

