 近年注目を集めているシニア採用ですが、人材の身体機能や健康面に不安を感じ、躊躇している企業も多いかもしれません。
近年注目を集めているシニア採用ですが、人材の身体機能や健康面に不安を感じ、躊躇している企業も多いかもしれません。
シニア採用には複数のメリットがあるため、採用手法のひとつとして取り入れると、自社にとってプラスの効果を得られる可能性があります。
この記事では、シニア採用の意味やメリット、課題と解決策、成功ポイントをまとめているため、採用活動の幅を広げるご参考にしてください。
| この記事でわかる事 |
|
・シニア採用が注目されている背景 ・シニア採用のメリット ・シニア採用の課題と解決策 ・シニア採用の成功ポイント |
|
「採用手法の比較表/自社にあった採用手法の選び方」をまとめたe-bookを無料提供中
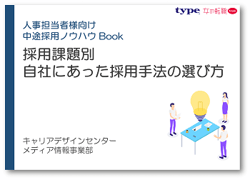 |
1.シニア採用とは |
シニア採用とは、定年退職した65歳以上の人材を採用する手法のことです。
令和7年(2025年)現在のシニア世代は、高度経済成長期やバブル経済期を経験しているため、人生経験が豊かな方や定年退職後も働く意欲の高い方が多い傾向があります。
シニア採用を行うことで、人材不足をカバーしながらシニアの知識や経験を事業に活かせるでしょう。
2.シニア採用が注目されている背景 |
シニア採用が注目されている背景として、次の3つが挙げられます。
|
・少子高齢化による労働力人口の変化 |
まずは、なぜシニア採用が注目されているのかを確認しましょう。
(1)少子高齢化による労働力人口の変化
日本は少子高齢化が進行しており、労働力人口にも変化が起きています。内閣府の「令和6年版 高齢社会白書」によると、令和5年(2023年)10月1日時点において、日本の総人口1億2435万人のうち、3623万人が65歳以上です。高齢化率は29.1%であり、昭和45年(1970年)の7%と比較すると約4倍も高くなっています。
一方、15~64歳の労働力人口は7395万人で、平成7年(1995年)の8716万人と比較すると約28年間で1300万人ほど減少していることがわかります。
今後も15~64歳の労働力人口は減少していくと予測されているため、65歳以上も労働力とみなし、採用することが企業の経営維持のために求められています。
(2)企業の人手不足
少子高齢化の進行は、企業の人材確保を困難にし、人手不足を誘発しています。株式会社東京商工リサーチの「人手不足に関するアンケート」調査によると、5割を超える企業が人手不足を原因として企業活動に支障が生じており、2024年には「人手不足倒産」が290件に達していることがわかりました。
企業の人手不足を解消するには、ダイバーシティを推進し、年齢や価値観の違いなどに左右されない多様性のある人材採用が求められます。シニア採用もダイバーシティ推進の一環であり、人手不足解消につながるため、シニアを採用候補とする企業も増えてきています。
| 💡ダイバーシティの意味と取り組むメリットについてまとめた記事はこちら |
(3)年金支給年齢の引き上げ
令和4年(2022年)4月から、老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。原則、年金は65歳から受け取れますが、66歳から75歳までの間に受給する「繰下げ受給」をすると、繰り下げた分年金額が増額されます。
日本年金機構によると、繰下げ受給の増額率は下記のとおりです。
| 請求時の年齢 | 増額率 |
| 66歳 | 8.4% |
| 67歳 | 16.8% |
| 68歳 | 25.2% |
| 69歳 | 33.6% |
| 70歳 | 42.0% |
| 71歳 | 50.4% |
| 72歳 | 58.8% |
| 73歳 | 67.2% |
| 74歳 | 75.6% |
| 75歳 | 84.0% |
年金の請求時期を繰り下げるほど受給できる年金額が増えるため、請求時期を遅らせても生活ができるようにできるだけ働き続けたいと思うシニアも多いでしょう。
実際に、内閣府の「令和6年版高齢社会白書(全体版)」における全国の60歳以上の男女に対して行われた「あなたは、何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいですか」という質問への回答割合を見てみると、収入のある仕事をしている人の場合、最も多いのが「働けるうちはいつまでも」36.7%で、次いで「70歳くらいまで」23.4%、「75歳くらいまで」19.3%となっています。
いわゆる高齢期になっても働く意欲の高い方が多いため、シニア採用に注目が集まっています。
3.シニア採用のメリット |
シニア採用には、次のようなメリットがあります。
|
・即戦力人材の確保 |
どのようなメリットを得られるのかをご紹介します。
(1)即戦力人材の確保
シニアのなかには、現役世代よりも長い年月特定の業務や業種に身を置いていた方もいます。培った経験やスキルは、即戦力として自社の人手不足をカバーしたり業績向上を図れたりするでしょう。
専門性の高い職種の場合、人材確保がより難しいと考えられるため、シニアのなかから即戦力人材を探してみると、技術も就労意欲もある人材を採用できるかもしれません。
(2)豊富な経験とスキルの活用
シニア採用の対象となるのは、人生経験豊富なシニア世代です。仕事・プライベート問わずにさまざまな経験をし、スキルを磨いてきたシニアは、予期せぬトラブルの発生にも冷静に対処できたり、若手人材の模範となって成長を促せたりする可能性があります。
また、若い上司が管理職経験のあるシニアにアドバイスを求めるケースもあります。さまざまな立場・年齢の方をサポートできるシニア人材は、企業にとってプラスの影響をもたらすでしょう。
(3)多様性の促進
前述のように、シニア採用は多様性の促進につながります。企業に多様性があると、さまざまな価値観を持つ人材の意見やアイデアでイノベーションを起こせるかもしれません。課題を抱えていた場合は、多角的な視点によってスピーディーに解決できる可能性もあります。
多様性を高めるときの不安要素として、従業員同士の円滑なコミュニケーションが挙げられますが、シニアのなかには、長年の仕事で多様な方々と接したことがある、子育てを経験しているという方もいます。豊富な人生経験のあるシニアであれば、相手の年齢や価値観などが自分と異なっても問題なくコミュニケーションを取れるでしょう。
(4)採用コストの抑制
シニア採用は、採用コストを抑えられるメリットがあります。例えば、自社の退職者を再雇用するアルムナイ採用を活用して定年退職者に声をかけると、求人掲載費などをかけずに人材募集ができるでしょう。
また、シニアはこれから結婚や子育てをするという可能性が低く、ライフステージの変化による離職が起きにくいです。働ける限り安定して働くという意識も高いため、就職後に経験を積みたいから転職する、条件のいい企業を積極的に探すなどのケースも少ないと考えられます。
人材が定着しやすいシニア採用は、離職による採用コストの増幅抑制につながるでしょう。
| 💡アルムナイ採用の意味と成功ポイントについてまとめた記事はこちら |
(5)助成金を受けられる
シニア採用を行うと、助成金を受けられるケースがあります。厚生労働省は、「65歳超雇用推進助成金」や「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」というシニア採用に関する制度を設けています。
それぞれの概要は下記のとおりです。
| 制度 | 概要 |
| 65歳超雇用推進助成金 |
下記3コースで構成 ②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ③高年齢者無期雇用転換コース |
| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |
60歳以上の高年齢者や重度障害者等、就職困難者を雇用する |
※2025年5月時点
助成金を受けられると、採用コストや整備コストの負担を軽減できます。支給条件や支給額等は細かく定められているため、制度を活用してシニア採用を検討する際には内容をよく確認しましょう。
4.シニア採用の課題と解決策 |
メリットの多いシニア採用ですが、高年齢者であることによる世代間のギャップや身体機能の低下など、さまざまな課題があります。
課題を抱えたままだと社内の空気が悪くなったり業務が停滞したりする恐れがあるため、解決することが重要です。
次の課題について、内容と解決策を解説します。
|
・シニアに対する偏見や先入観 |
(1)シニアに対する偏見や先入観
シニアに対する偏見や先入観から、コミュニケーションを避けたり業務の教えづらさを感じたりする従業員がいるかもしれません。例えば、「シニアはITの話題についてこれない」「シニアはパソコンを使うのが苦手だ」という偏見があると、シニアを会話に混ぜない、パソコンを使う業務を教えるのが面倒で教えないなどのネガティブな事態を招く恐れがあります。
一方で、シニアが若手人材に偏見を持っているケースもあります。「年長者への礼がなっていない」「経験豊富な自分が指導しないとダメだ」などの思い込みによって、若手人材へ厳しく接したり自分が新入社員にも関わらず業務の指示を出したりするかもしれません。
偏見や先入観は、人間関係の不和やコミュニケーションの消失、業務の停滞につながるため、取り払うことが重要です。
解決策
従業員全体の偏見や先入観をなくすために、意識改革を行いましょう。「年齢」で相手を見ず、お互いを尊重する姿勢を保てるように、異なる部分や経験値の違いを受け入れることが大切です。具体的には、意識改革の目的や必要性を周知する、上位者が積極的に多様な従業員とコミュニケーションをとる、目標を立てるなどが挙げられます。
また、採用したシニアには「自社における役割」や「期待していること」を明確に伝えると、役割を超えた言動の抑制となり、周りにマイナスな印象を与えずに自分の能力を発揮してくれるでしょう。
(2)デジタル機器の操作や業務内容の習得
シニアが現役で働いていた時代は主にアナログ業務であり、デジタル機器も普及していなかったため、PCやITツールなどに不慣れな傾向があります。使えたとしても活用範囲が限定的で、業務に活かせないことも考えられます。
内閣府の「令和3年版高齢社会白書(全体版)」によると、日本の60歳以上の方が情報機器を使う主な目的は連絡手段です。アメリカ含む各国と比較すると、情報収集やネットショッピング、SNS、ブログ等の利用は低いことがわかります。情報機器を使わない理由については、「使い方が分からないので、面倒だから」が半数を超えており、あえて避けている傾向も見られます。
高年齢化に伴う脳機能の低下によって、業務内容を短期間で覚える、柔軟に発想するなどができずに、業務の習得に時間を要したり円滑な業務が難しかったりすることも課題のひとつです。
解決策
デジタル機器の操作を必要とする業務の場合、シニアでもわかりやすいマニュアルの作成や研修によって、理解を促すことが求められます。例えば、イラストを用いたり文字サイズに配慮したりすると、読みやすくなるでしょう。
業務内容についても、メンターをつける、チームでサポートするなどの教育体制を整備して気軽に相談や確認ができる環境をつくると、シニアの理解が進み、戦力化が加速します。
(3)身体機能や健康面の不安
厚生労働省の「令和5年 高年齢労働者の労働災害発生状況」によると、労災による休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の割合は29.3%で、男性は「墜落・転落」、女性は「転倒による骨折等」の割合が高い傾向があります。
シニアは、身体機能や免疫力の低下によって、ほかの従業員よりもケガや病気のリスクが高く、労災や体調不良等の不安が生じやすいです。
リスク防止の観点から、シニア採用に慎重になる企業も多いでしょう。
解決策
シニア採用によるケガや病気のリスクを軽減するには、職場環境の改善や健康診断の実施が効果的です。厚生労働省が策定した「エイジフレンドリーガイドライン」では、次のような取り組みが挙げられています。
|
【職場環境の改善例】 【健康面での配慮】 |
健康診断は、企業だけでなくシニアが自分の健康状態を把握できる手段としても重要です。
また、体力も客観的に把握できるように、継続的な体力チェックを実施し、安全に作業できる体力水準を満たしていないシニアに対しては体力向上を促しましょう。併せて職場の安全対策にも取り組むと、安全かつ健康的に働いてもらえる可能性があります。
5.シニア採用の成功ポイント |
シニア採用を成功させるには、前述のシニア採用の課題を解決するほか、下記3点についても意識することが大切です。
|
・雇用条件や勤務形態を柔軟に変更する |
各ポイントを確認して、シニア採用を成功に導きましょう。
(1)雇用条件や勤務形態を柔軟に変更する
一般の求職者と同様に、シニアのなかにもフルタイムで働く意欲がある方、家庭や体調の都合で短時間で働きたい方など、働き方への要望はさまざまです。そのため、正社員だけでなく、原則転勤がない契約社員や、正社員よりも労働時間が短い短時間正社員など、雇用条件を柔軟にしましょう。
また、勤務形態も、シニアがワークライフバランスを保ちながら働けるように、フレックスタイム制度やリモートワーク制度などの働き方を複数用意し、状況に応じて柔軟に変更することが望ましいです。
(2)業務内容に配慮した働きやすい環境を作る
身体機能が低下しているシニアは、若手人材と同じように働けるとは限らないため、配属部署や業務内容に配慮しましょう。例えば、力仕事がメインの部署への配属や目で細かいものを見る作業を避ける、通常1人で取り組む作業を2人体制にするなどの検討が必要です。
シニアが働きやすい環境であれば、自分の能力を発揮しながら活き活きと業務へ取り組んでもらえるでしょう。また、ケガなどのリスクも抑えられます。
(3)適材適所に配置する
業務内容に配慮する一方で、シニア個々人の特性を見極め、適材適所への配置や本人の希望を反映した業務提供なども大切です。シニアが培ってきたスキルや経験を活かせる業務であれば、即戦力としての活躍やモチベーションの高い取り組みで、生産性の向上が期待できます。
新しいことや難しい業務へ挑戦したいというシニアに対しては、希望の業務を任せると大きな成長を見込めるかもしれません。シニアが望む業務をヒアリングして、人材配置を検討するといいでしょう。
6.まとめ |
少子高齢化により労働力人口が変化している現代において、シニア採用は企業の人手不足解消や多様性の促進につながる採用手法です。
シニア採用には、身体機能の低下による労災リスクの増加という課題があるため、職場環境を改善して安全を確保することが求められます。また、柔軟な雇用条件や勤務形態を用意することも、シニア採用の成功につながる大切なポイントです。
いかがでしたか。もし中途採用について悩まれている、自社にとって適切な手法が分からないといった場合は、ぜひ弊社キャリアデザインセンターにご相談ください。エンジニア採用・女性採用に特に強みを持ち、あらゆる中途採用ニーズに対応できるサービスを運営しております。
サービスの詳細については、下記弊社中途採用サービス概要のご案内ページをご覧ください。
#シニア採用
|
type公式中途採用向けサービス案内サイト 【公式】type中途採用向けサービスのご案内|転職サイト、転職エージェント、派遣サービスなど 運営会社 株式会社キャリアデザインセンター 会社概要 コーポレートサイト:https://cdc.type.jp/
事業内容
・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営 ・転職フェアの開催 ・人材紹介事業(厚生労働大臣許可 13-ユ-040429) ・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス ・パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業 ・IT業界に特化した人材派遣サービス(厚生労働大臣許可 派13-315344) ・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営 など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。
法人企業様向けお問い合わせ先
・フォームでのお問い合わせ |
著者プロフィール
ブログ編集部
「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。
■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/
■企業様向け公式SNS:

