
オフボーディングとは、退職希望者の円満退職を実現する取り組みのことです。退職面談の実施や退職手続きのサポートによって、退職に関する不安を取り除いたりスムーズに退職日を迎えられるようにしたりします。
さまざまな効果を得られるオフボーディングですが、取り組みの際には注意点もあるため、事前に確認しておきましょう。
オフボーディングの意味やオンボーディングとの違い、メリット、具体的な進め方と注意点を解説します。
| この記事でわかる事 |
|
・オフボーディングの意味 ・オフボーディングの効果・メリット ・オフボーディングの具体的な進め方 ・オフボーディングで注意すべきポイント |
|
「採用手法の比較表/自社にあった採用手法の選び方」をまとめたe-bookを無料提供中
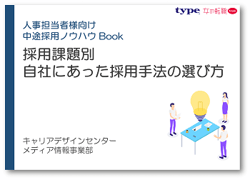 |
1.オフボーディングとは |
オフボーディングとは、退職希望者に対して退職に関する手続きや業務の引継ぎをサポートし、円満退職を実現する取り組みのことです。
オフボーディングを実施すると、退職者は企業に対してポジティブな感情を抱いたまま退職できるため、良好な関係性の維持につながります。
(1)オフボーディングが必要とされる背景
オフボーディングが必要とされる背景には、次の3つがあります。
|
・人材の流動性の高まり |
人材の流動性の高まり
人材の流動性が高まり、転職が一般化している現代において、退職者が自社と今後も関わる可能性はゼロではありません。例えば、退職者が取引先へ就職したり将来のビジネスパートナーになったりするケースがあります。
また、自社商品やサービスの顧客になる、すでに顧客で関係性が構築されているなども考えられるため、退職者との良好な関係維持を図れるオフボーディングは重要です。
情報発信や収集が容易にできる環境
インターネットやSNSが普及し、誰でも容易に情報発信や収集ができる環境は、企業の退職時のネガティブな対応も簡単に拡散、周知され、企業イメージの低下を招くでしょう。
また、転職・就職にあたり、インターネットやSNSで企業の評判や口コミを調べる求職者は多いため、応募数も減少する恐れがあります。
社会的な信用や信頼を損なわないように、オフボーディングを実施することが望ましいです。
アルムナイ採用の一般化
アルムナイ(退職者)採用とは、自社の退職者を再雇用することです。労働力人口の減少や人的資本経営の考え方の普及などを背景に、アルムナイ採用が一般化してきています。
アルムナイ採用を成功させるには、退職者が再度自社で働きたいと思えるように円満退職を実現することが大切なため、オフボーディングが重要視されています。
| 💡アルムナイ採用の意味と成功ポイントについてまとめた記事はこちら |
(2)オンボーディングとの違い
オンボーディングとは、新入社員が自社に慣れ、早期に活躍できるようサポートする取り組みのことです。
一方のオフボーディングは、退職希望者が円満退職できるようにサポートする取り組みのため、対象者や内容に大きな違いがあります。
| 💡オンボーディングの意味と導入方法についてまとめた記事はこちら |
2.オフボーディングの効果・メリット |

オフボーディングに取り組むと、次のような効果・メリットを得られる可能性があります。
|
・離職率の改善 |
オフボーディングの効果・メリットを確認しましょう。
(1)離職率の改善
オフボーディングは、退職意思のある従業員との面談を行うのが一般的で、退職理由のヒアリングによって自社の業務や体制、職場環境の問題点を把握できる可能性があります。
ヒアリングした内容から職場環境や制度などを整備することで、既存従業員の働きやすさが向上するため、離職率の改善が期待できます。
(2)企業イメージの向上
退職希望者に対して丁寧なサポートをするオフボーディングは、従業員として最後まで大切にしてくれる企業という印象を社会に与えるため、企業イメージを向上させるメリットがあります。
企業イメージが向上すれば、求人への応募や顧客の増加が期待できるでしょう。
(3)退職者からのフィードバックを得られる
オフボーディングで円満退職を実現できた場合、退職者は自社に対して好印象を抱いているため、自社商品やサービスに対するポジティブなフィードバックをしてくれるかもしれません。
自社商品・サービスを熟知している退職者の社外からの視点によるフィードバックは、企業のさらなる成長につながる可能性があります。
(4)アルムナイネットワークを構築できる
アルムナイネットワークとは、企業が退職者と接点を持ち続けるコミュニティのことです。例えば、社内イベントの実施や社内SNSなどの活用によって、退職者や既存従業員がコミュニケーションを取る機会を設けています。
アルムナイネットワークを構築できると、アルムナイ採用の難易度が下がったり、起業した退職者と新たなビジネス関係を築けたりと、事業展開や拡大を図れるかもしれません。
オフボーディングに取り組めば、退職者がアルムナイネットワークに参加してくれる可能性が高まるため、より多くの退職者とのつながりを維持できます。
(5)従業員のモチベーション向上
オフボーディングによって浮き彫りになった職場環境の問題点を改善していけば、既存従業員は働きやすくなり、自社に対する不満が減るため、貢献意欲やモチベーションが向上するでしょう。
高いモチベーションで取り組む業務は、効率や生産性を上げることにつながり、従業員と企業の双方に好循環をもたらします。
3.オフボーディングの具体的な進め方 |

オフボーディングは、次の5つのステップで進めていきます。
|
①退職の意思確認と初期面談 |
各ステップを具体的に解説します。
(1)退職の意思確認と初期面談
従業員から退職の意思表示があった場合、初期面談を実施して退職理由をヒアリングします。退職理由を本音で話してもらえるように、退職意思を否定しないこと、傾聴と共感を心掛けることを意識しましょう。
退職理由や状況によっては退職を引き留めたいケースもありますが、怒ったり強引な方法をとったりするとマイナスな印象となるため、意思を尊重して対応することが大切です。
従業員の退職時期や退職までの仕事に対する希望も聞いて、可能な限りサポートしていきます。
(2)情報共有と引継ぎの準備
退職希望者と関わりのある部署や従業員に情報を共有し、引継ぎの準備をします。情報を早めに共有すると引継ぎにかけられる時間が長くなるため、退職日までに間に合わなかったという事態を防げるでしょう。
引継ぎの例として、業務内容や手順、顧客情報をまとめた資料の作成、月単位や年単位の業務プロセスの整理と提示、取引先や顧客への挨拶、引継ぎ書類の後任者への説明などが挙げられます。
通常業務と並行しながらの引継ぎは退職希望者にとって負担となるため、スムーズな引継ぎを実現できるようにサポートしましょう。
(3)退職面談の実施
二回目の面談となる退職面談では、自社に対する不満や課題などをヒアリングします。職場環境や業務、評価制度、働き方など、多角的な面からフィードバックを受けることで、効果的な改善につなげられます。
また、退職手続きや引継ぎに関する悩みの有無も確認し、悩み解消につながる説明やアクションを起こすことも大切です。
(4)最終手続きと環境整備
退職日の直前や当日には、最終手続きと環境の整備を行います。
失業手当の受け取りや転職活動をスムーズにできるように、離職票などの必要書類をあらかじめ用意しておきましょう。貸与していた制服や備品の回収、社内ファイルへのアクセス権の削除なども忘れないように注意が必要です。
事務的な面だけでなく、退職希望者への送別会を開催して精神面もフォローすると、自社に対するよい印象を維持したまま退職日を迎えてもらえるでしょう。
(5)退職後のフォローアップ
退職者が失業手当の受給などの手続きを早期にできるように、用意していた必要書類を迅速に送付して、対応の遅れによるマイナスな印象を防ぎます。
また、アルムナイネットワークへ参加してもらって、社内イベントやSNSなどで定期的に交流を図り、良好な関係の維持に努めます。
4.オフボーディングで注意すべきポイント |

オフボーディングを成功させるには、従業員に不快な思いをさせないことが重要です。
オンボーディングで注意すべき次の3つのポイントをご紹介します。
|
・退職することを否定しない |
(1)退職することを否定しない
退職希望者に対して、退職することを否定しないようにしましょう。例えば、退職の意思を告げられた際に「あなたには多くのコストをかけたのに」「あなたがいなくなると業務が停滞するから困るんだよ」などとネガティブな思いをぶつけると、退職希望者は信頼をなくしてしまう可能性が高いです。
自社への思いが急降下し、アルムナイネットワークへの不参加だけでなくマイナスな口コミ投稿などの好ましくない事態を招く恐れもあるため、退職意思を尊重し、寄り添う姿勢を心掛けましょう。
(2)退職希望者の本音を引き出す
退職希望者のなかには、スムーズな退職を目指して本音を隠す方もいます。例えば、業務への不満が退職理由の場合、部署異動を提案され引き止められることを想定して、企業が介入しづらい個人的な理由を伝えるケースがあります。
退職希望者の本音を引き出せないと自社の問題の洗い出しができず、新たな退職者を生むかもしれないため、退職希望者が本音を話しやすいようにリラックスできる空間を用意するなどの工夫が必要です。
また、面談担当者を変えることも本音を引き出すのに効果的です。例えば退職理由が上司からのハラスメントの場合、面談相手が「加害者である上司」と「人事担当者」では、人事担当者相手のほうが本音を話してもらえる可能性があります。そのため、面談で本音を引き出せなければ、状況に応じて担当者を変えて再面談することも検討しましょう。
(3)法律や就業規則に基づいて手続きをする
従業員の退職手続きは、法律や就業規則に基づいて行う必要があります。退職金制度がある企業の場合、不当な減額や不支給などせず、適切に退職金を支払いましょう。
民法では、雇用形態にもよりますが従業員の退職を拒否できないため、「この企画が終わるまでは退職させない」など違法な引き止めはトラブルの元です。退職日までの有休取得も原則拒否できません。
退職希望者との禍根を残さないように、真摯に対応することが大切です。
5.まとめ |
オフボーディングは、円満退職を実現するために、退職希望者に対して退職の手続きなどをサポートする取り組みのことです。
オフボーディングの効果としては、企業イメージの向上やアルムナイネットワークの構築などが挙げられます。退職者との良好な関係性を維持できるように、退職の意思を尊重しつつ、法律に基づいた適正な退職手続きを行いましょう。
いかがでしたか。もし中途採用について悩まれている、自社にとって適切な手法が分からないといった場合は、ぜひ弊社キャリアデザインセンターにご相談ください。エンジニア採用・女性採用に特に強みを持ち、あらゆる中途採用ニーズに対応できるサービスを運営しております。
サービスの詳細については、下記弊社中途採用サービス概要のご案内ページをご覧ください。
#オフボーディング
|
type公式中途採用向けサービス案内サイト 【公式】type中途採用向けサービスのご案内|転職サイト、転職エージェント、派遣サービスなど 運営会社 株式会社キャリアデザインセンター 会社概要 コーポレートサイト:https://cdc.type.jp/
事業内容
・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営 ・転職フェアの開催 ・人材紹介事業(厚生労働大臣許可 13-ユ-040429) ・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス ・パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業 ・IT業界に特化した人材派遣サービス(厚生労働大臣許可 派13-315344) ・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営 など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。
法人企業様向けお問い合わせ先
・フォームでのお問い合わせ |
著者プロフィール
ブログ編集部
「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。
■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/
■企業様向け公式SNS:

