
退職代行はいまや世間一般的に認知されているサービスですが、使われたときの対応方法を知っているという企業は多くないかもしれません。
退職代行を使われた際には、適切に対応しないと法令違反となる恐れがあるため、注意が必要です。
退職代行サービスの企業への影響と対応方法、注意点、未然に防ぐ対策について解説します。
| この記事でわかる事 |
|
・退職代行サービスが企業に与える影響 ・退職代行を使われたときの対応方法 ・退職代行を使われたときの注意点 ・退職代行サービス利用を未然に防ぐための対策 |
|
「採用手法の比較表/自社にあった採用手法の選び方」をまとめたe-bookを無料提供中
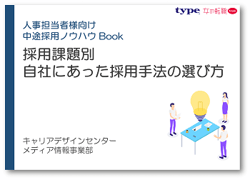 |
1.退職代行サービスとは?人事担当者が知るべき現状と背景 |
退職代行サービスとは、退職を希望する従業員の代わりに、弁護士などが退職の意思を企業に伝える有料サービスのことです。例えば、「上司のパワハラ」や「退職の強引な引き止め」などを理由に自ら退職することが困難なケースで、退職代行サービスが利用されています。
従業員から退職の意思があった場合、企業は原則拒否できません。退職代行サービスを利用した退職であっても同様です。
(1)退職代行サービスが注目される背景
退職代行サービス「退職代行モームリ」を提供する株式会社アルバトロスの調査によると、退職代行を利用する理由の1位は「上司から各種ハラスメントを受けている」次いで「上司から退職を止められる」でした。年齢は20代が多く、どの年代でも男女の利用率に大きな差はありません。
退職代行サービスが注目を集め、利用される背景には下記が挙げられます。
|
・企業側から退職の引き留め |
企業側から退職の引き留め
企業の人員不足や、退職する社員が重要なポジションや業務をこなしていた場合に、退職を希望しても企業側が引き留めを行うケースもあります。
前述の調査における「退職代行を利用する理由」の上位も自力退職の難しさがあるため、自分の心身や限りある時間を守る手段として、退職代行サービスが注目されています。
対面コミュニケーションの減少
新型コロナウィルスの蔓延やインターネットの普及によって、オンラインでのコミュニケーションが増加し、対面コミュニケーションに苦手意識を持つ方も少なくありません。
退職意思を直接伝えることにハードルの高さを感じる方にとって、自分の代わりに退職意思を伝えてくれる退職代行サービスは便利なため、利用される傾向があります。
(2)退職代行サービスの主な形態3種類
退職代行サービスを行なっているのは、主に次の3つです。
|
・弁護士 |
それぞれの特徴や対応範囲をご紹介します。
弁護士
弁護士が行う退職代行サービスは、対応範囲が広いのが特徴です。
| 対応範囲例 |
・退職意思の伝達 |
弁護士法72条では、弁護士の有資格者しかできないと法的に定められている行為を無資格者が報酬を得る目的で行うこと(非弁行為)を違法としています。
例えば「未払い残業代の請求」や「損害賠償請求」「労働審判・裁判」は弁護士しか対応できないため、企業とのトラブルを抱えている、もしくはトラブルを危惧する従業員が利用を検討しやすいでしょう。
退職代行ユニオン
ユニオンとは、自社に労働組合がない方でも加入可能な「社外にある労働組合」のことで、労働者であれば雇用形態に関係なく一人でも加入できるという特徴があります。
ユニオンは労働組合法によって保護されており、団体交渉権も認められているため、退職意思の伝達だけでなく交渉も可能です。ただし、企業との交渉が難航し、裁判など法的な事態にもつれ込んだ場合は対応できません。
| 対応範囲例 |
・退職意思の伝達 |
退職代行ユニオンは、企業と裁判などのトラブルになるリスクが低い一方で、スムーズな退職に懸念がある従業員が利用すると考えられます。
民間業者
民間業者が提供している退職代行サービスの対応範囲は、従業員の退職意思を代わりに企業へ伝達することです。
弁護士や退職代行ユニオンのように特有の権利がないぶん、弁護士に監修してもらい法的リスクを抑えたり、労働組合と提携し、提携先の労働組合が主体として交渉を行っているケースもあります。
| 対応範囲例 |
・退職意思の伝達 |
民間業者の退職代行サービスは、退職までのハードルが低い従業員が利用しやすいでしょう。
なお、退職意思をただ伝えるのみであれば非弁行為に該当せず、違法性はないと考えられています。
2.退職代行サービスが企業に与える影響 |

退職代行サービスが使われた場合、企業への影響として次の3つが挙げられます。
|
・ネガティブなイメージの定着 |
退職代行サービスが企業に与える影響を解説します。
(1)ネガティブなイメージの定着
退職代行は、「ハラスメントがある」「退職届を受け取ってもらえない」などの理由で利用される場合があります。そのため、従業員に退職代行を使われた場合、「退職意思を直接伝えられない職場環境なのではないか」のようにネガティブなイメージを持たれてしまう可能性があります。
(2)従業員エンゲージメントの低下
「退職代行を使われる」という状況は、世間一般的によいイメージがなく、従業員の自社に対するイメージも悪くなると考えられます。
自社に対する信頼感の低下に伴い、モチベーションやエンゲージメントも下がってしまう可能性があります。
(3)人材流出の加速
退職代行を使われた場合、利用した従業員は有休を取得するなどして退職日まで出社しないことが一般的なため、当該従業員が担当していた業務をほかの従業員が引き継がなければなりません。ほかの従業員は、業務量の増加に加え、引き継ぎもされていないという状況がスムーズな業務を阻害し、ストレスも増えるでしょう。
「自社が退職代行を使われた」という事実にエンゲージメントが低下している可能性があるなか、業務やストレスの負荷がかかることで、さらに人材が流出する恐れがあります。
3.退職代行を使われたときの対応方法 |

従業員に退職代行を使われたときには、下記の手順で対応していきます。
|
①退職代行サービスの身元を確認する |
なお、前述のように、従業員から退職の申し出があった場合は、連絡してきたのが退職代行であっても原則拒否できません。
退職申し出への対応は、従業員の雇用形態によって異なります。
| 雇用形態 | 退職申し出への対応 |
| 無期雇用 |
退職日の2週間前に退職意思を企業へ伝えていれば、退職を拒否できない |
| 有期雇用 |
原則、契約期間の途中であれば退職を拒否できる |
ここでは、退職を拒否できないケースの対応方法をご紹介します。
(1)退職代行サービスの身元を確認する
退職代行サービスは、一般的に電話で連絡をしてきます。退職代行サービスから連絡が来たら、まずは身元を確認しましょう。退職代行サービスの形態によって、退職意思を伝えるのみなのか、退職に関する交渉までできるのかなどが異なるため、身元確認をして自社が取るべき対応を確立することが大切です。
| 退職代行サービスの身元 | 具体的な対応方法 |
| 弁護士 |
従業員の退職手続きを行う |
| 退職代行ユニオン |
従業員の退職手続きを行い |
| 民間業者 |
従業員の退職手続きを行う |
また、イタズラや詐欺の可能性も考慮し、相手が実在するか、正規の弁護士やユニオンかの確認も求められます。連絡が来たら、相手の名称や担当者名などの情報をヒアリングして一旦電話を切り、確認後に折り返し電話をするという慎重な対応が必要です。
(2)従業員本人の意思を確認する
退職代行サービスを利用した従業員に、退職の意思が本当にあるのかを確認します。悪意ある第三者によって退職代行が使われているケースもあるため、本人の意思確認は重要です。
意思確認の方法としては、本人への電話やメールでの連絡が挙げられますが、本人が退職代行を使っている場合は応えてくれない可能性が高いです。そのため、直接の連絡が難しければ退職代行サービスに委任状や本人の身分証明書などを提示してもらい、意思確認をしましょう。リスク回避策として、本人の意思確認ができない限りは退職手続きを慎重に進めることが重要です。提示された委任状や身分証明書などを確認し、退職代行サービスが正当な手続きを踏んでいるかを見極めることが大切です。
(3)退職届を提出してもらう
従業員本人の意思確認ができたら、自社の就業規則に則り、退職届を決められた書面などで作成・提出してもらいます。
送られてきた退職届に不備がないか確認し、必要に応じて再提出を求めましょう。
(4)業務の引き継ぎを依頼する
退職する従業員に、業務の引き継ぎを依頼します。退職する従業員しかできない業務がある、業務に必要な資料や道具を持っているなどの場合、今後の円滑な業務進行に支障が出るため、引き継ぎが必要です。
出社での引き継ぎができない状況であれば、業務マニュアルを作成してメールや郵送で送ってもらう、資料や道具の置き場所を教えてもらうなどの対応を求め、引き継ぎ漏れによるリスクを回避します。
(5)貸与物の返還手続きを行う
制服や業務用PC、社員証、名刺、鍵など、企業から従業員への貸与物があれば、返還手続きを行いましょう。従業員が直接企業へ返還に来ることは難しいと考えられるため、郵送してもらうケースが多いです。
また、従業員の私物が社内にある場合は、郵送や廃棄など、従業員の意向を確認してから対応します。
貸与物や私物に関する郵送代は、退職する従業員負担としてもいいですが、従業員と企業のどちらが負担するかをあらかじめ決めておいたほうが、無用なトラブルを招かずに済むでしょう。
(6)退職届を受理する
提出を依頼していた不備のない退職届を受理したら、退職手続きを進めていきます。
退職手続きを完了したら、従業員へ完了した旨の連絡をしましょう。メールや書面で連絡すると証拠として残るため、トラブル回避につながります。
|
「採用手法の比較表/自社にあった採用手法の選び方」をまとめたe-bookを無料提供中
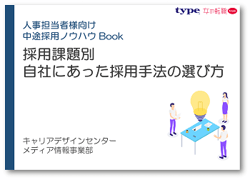 |
4.退職代行を使われたときの注意点 |

もし自社が退職代行を使われた際には、下記3点に注意が必要です。
|
・弁護士やユニオン以外とは退職交渉しない |
退職代行サービスから電話がかかってきて焦らないように、確認して心構えをしておきましょう。
(1)弁護士やユニオン以外とは退職交渉しない
弁護士やユニオン以外の退職代行サービスから連絡があった場合は、退職の意思の伝達のみであれば、これを受け入れることになります。
ただし、これらの業者には退職条件に関する交渉権限がないため、条件交渉には応じる必要はありません。 しつこく交渉を求められる、あるいは交渉を拒否した際に脅迫などの問題行為があった場合は、速やかに弁護士へ相談してください。必要に応じて、法的措置を検討することも視野に入れましょう。
(2)有給休暇を消化させる
退職代行を使われたときに、従業員が有給休暇の取得を申請するケースもあります。労働基準法では、労働者が申請する時季に有休を与えなければならないとしているため、従業員から有休の取得申請があった場合は原則として拒否できません。
なお、有休の取得時季が「事業の正常な運営を妨げる」場合は、時季変更権を行使してほかの時季に有休の取得日を変更することができますが、退職日が近い従業員には適用が難しいと考えられます。
そのため、法に違反しないためにも、従業員から有休を申請されたら許可しましょう。自社が有休の買い取り制度を設けている場合は、規定に従って買い取る等、適切に対応することが大切です。
(3)速やかに退職処理を行う
退職代行を使われたら、速やかに退職処理を行いましょう。退職手続きを意図的に遅らせるような対応は、会社のイメージを大きく損なう可能性があります。
現代では、SNSやインターネット上で企業の評判が容易に拡散されます。退職者への丁寧な対応を心がけることは、不必要な悪評を防ぎ、結果として企業の信頼性を維持するために重要です。
| 💡求職者が口コミチェックする理由と対策についてまとめた記事はこちら |
5.退職代行サービス利用を未然に防ぐための対策 |

退職代行サービスを利用する従業員は、企業に対して何らかの不満を抱いていると考えられます。
しかし、不満がわからないと対策ができず、ある日突然退職代行サービスから電話がかかってきた、ということになりかねません。
そのため、従業員の「不満を知る」「不満を発生させない」ために、次の対策を施しましょう。
|
・離職理由を分析する |
それぞれ詳しく解説します。
(1)離職理由を分析する
退職代行サービスの利用に限らず、過去に退職した従業員の離職理由を分析しましょう。人間関係の不和、ハラスメント、働きにくさなど、自社にどのような問題があって従業員が離職したのかがわかると、対策を立てやすくなります。
一方で、離職理由が本音とは限らないため、より正確な離職理由の特定につながるように、従業員のメンタルヘルスやエンゲージメントの定期的な測定を取り入れ、在籍中から心の変化を把握することが大切です。
(2)従業員とのコミュニケーションを密に行う
退職代行を使う従業員のなかには、精神的に追い詰められ、職場の人と話したくないと思っている方もいます。職場の風通しの悪さや重苦しい雰囲気、パワハラ気質などが退職代行サービスを使うまでに追い込んでいる可能性があるため、コミュニケーションが活発な、風通しのよい職場環境にすることが望ましいです。
例えば、次のような施策を取り入れるとコミュニケーションが活性化され、従業員同士が協力する体制や悩みを相談しやすい環境を構築できるでしょう。
コミュニケーションを活発にする施策例・フリーアドレスの導入 |
(3)労働環境を整備する
労働環境の整備も、退職代行サービスを使われないために重要な取り組みのひとつです。フレックスタイム制度やリモートワークなどの柔軟な働き方を導入する、働きやすいように机や備品の位置を整える等、従業員の働きやすさやモチベーションが向上するような工夫を施しましょう。
従業員へヒアリングして本音を引き出すと、取り組みの優先順位が明確になります。従業員を大切にする姿勢を示し、重要なものから改善していくことで、従業員の自社に対する満足度を高めましょう。
6.まとめ |
もし退職代行サービスを使われた際には、相手が民間業者なら交渉には応じないなど、サービス形態ごとの特徴を理解し、適切に対応しましょう。
退職代行サービスを使われた場合、企業イメージや従業員エンゲージメントの低下といったネガティブな影響があるため、そもそも使われないように職場環境を改善し、従業員の自社への愛着や満足度を高めることが重要です。
いかがでしたか。もし中途採用について悩まれている、自社にとって適切な手法が分からないといった場合は、ぜひ弊社キャリアデザインセンターにご相談ください。エンジニア採用・女性採用に特に強みを持ち、あらゆる中途採用ニーズに対応できるサービスを運営しております。
サービスの詳細については、下記弊社中途採用サービス概要のご案内ページをご覧ください。
#退職代行 #退職代行サービス
|
type公式中途採用向けサービス案内サイト 【公式】type中途採用向けサービスのご案内|転職サイト、転職エージェント、派遣サービスなど 運営会社 株式会社キャリアデザインセンター 会社概要 コーポレートサイト:https://cdc.type.jp/
事業内容
・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営 ・転職フェアの開催 ・人材紹介事業(厚生労働大臣許可 13-ユ-040429) ・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス ・パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業 ・IT業界に特化した人材派遣サービス(厚生労働大臣許可 派13-315344) ・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営 など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。
法人企業様向けお問い合わせ先
・フォームでのお問い合わせ |
著者プロフィール
ブログ編集部
「エンジニア採用情報お届けブログ」「女性採用情報お届けブログ」「中途採用情報お届けブログ」は、株式会社キャリアデザインセンター メディア情報事業部「type」「女の転職type」が運営する採用担当者様向けのブログです。構成メンバーは、長年「type」「女の転職type」を通して様々な業界の企業様の中途採用をご支援してきたメンバーになります。本ブログを通して、多くの企業様の中途採用にお役立てできるよう情報発信してまいります。
■運営会社:株式会社キャリアデザインセンター https://cdc.type.jp/
■企業様向け公式SNS:

